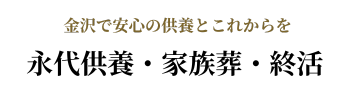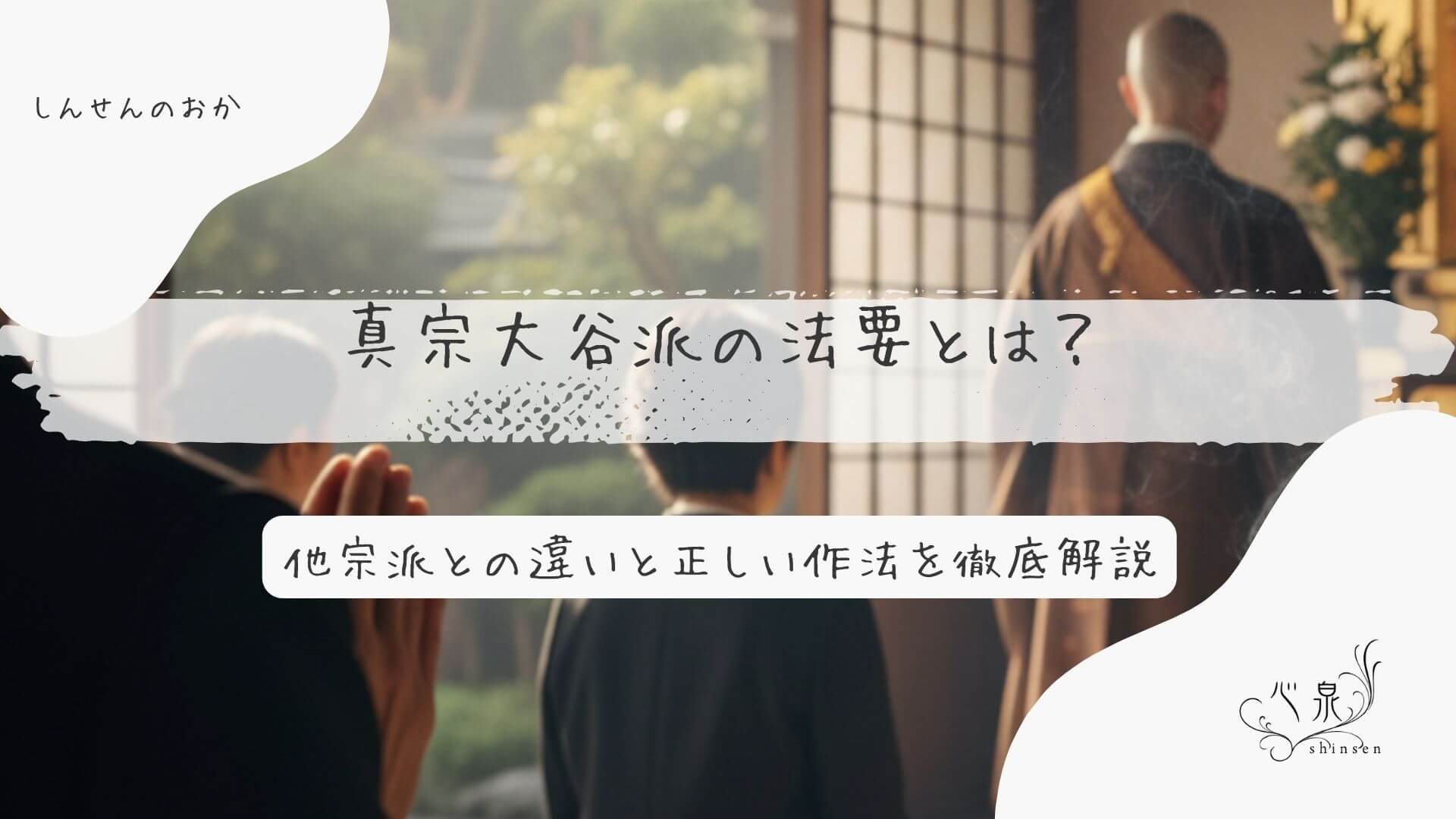「法要の準備、これで合っているのかな…」
そう感じながらも、誰に聞けばよいか分からず不安を抱える方は少なくありません。
特に真宗大谷派(しんしゅうおおたには)では、他宗派とは少し異なる考え方や作法があり、事前に知っておくと心の余裕を持って当日を迎えられます。
真宗大谷派の法要は、故人の冥福を祈る儀式ではなく、阿弥陀如来のはたらきに感謝する場として行われます。
形よりも「心」を大切にし、手を合わせる時間そのものに意味があります。
この記事では、真宗大谷派の法事・法要の基本的な流れや作法、他宗派との違いをわかりやすく解説します。
読んでいただくことで、形式にとらわれず、安心して心を込めた供養を行うための理解と準備が整います。
真宗大谷派の法要は「故人を追悼する儀式」ではなく「感謝を伝える場」
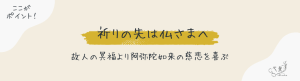
真宗大谷派では、法要は故人の冥福を祈る儀式ではなく、阿弥陀如来の慈悲に感謝する場として行われます。
「亡くなった人のために祈る」のではなく、「仏さまの教えに導かれて、生かされていることに気づく時間」なのです。
この考え方は「報恩講(ほうおんこう)」という言葉に表れています。
報恩講とは、阿弥陀如来や親鸞聖人への感謝を表す法要で、真宗大谷派では最も大切にされています。
つまり法要は、悲しみを癒やすだけでなく、“いのちのつながり”を感じる時間でもあります。
亡くなった方を通して、「生きること」「感謝すること」を改めて見つめ直す機会として受け止めましょう。
真宗大谷派の法事・法要の流れは「読経中心」でシンプルに構成されている
真宗大谷派の法要は、形式にとらわれず、読経と焼香を中心に静かに進行します。
僧侶による読経(正信偈・念仏・和讃など)を通して、仏さまの教えを聞き、心を整えるのが目的です。
一般的な流れは次の通りです。
|
手順 |
内容 |
説明 |
|
① 開式 |
僧侶と遺族が合掌して開式の挨拶 |
故人ではなく仏さまに向かう姿勢 |
|
② 読経 |
正信偈や念仏を唱える |
心静かに仏法を味わう時間 |
|
③ 焼香 |
一人ずつ合掌して焼香 |
回数は2回が基本 |
|
④ 法話 |
僧侶からの仏教のお話 |
感謝や生き方への気づきを深める |
|
⑤ 閉式 |
合掌・礼拝・挨拶 |
阿弥陀如来の教えに感謝して終了 |
流れはとても穏やかで、静かな時間が心に残るのが特徴です。
「正しくしよう」と構えすぎず、「心を込めて手を合わせる」ことを大切にしましょう。
焼香は「1回」が基本|真宗大谷派では回数より心を込めることが大切
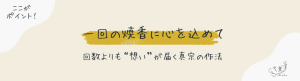
焼香は、仏さまへの感謝を表す行為であり、真宗大谷派では「回数」よりも「心」を重んじます。正式な作法では、焼香は1回が基本です。
焼香の方法は以下の通りです。
- 数珠を左手にかけ、右手の3本の指で香をつまむ
- 額にいただかず、寝かせた線香の上ではなく、香炉へくべます
- 合掌して礼拝
ほかの宗派では1回や3回の場合もありますが、真宗大谷派では「二度で心を込める」ことに意味があります。
香を焚くことは、仏さまの教えに導かれて生きる姿勢を表す行いでもあります。
供物やお供えは「見栄えよりも清らかさ」|華美な飾りより心を重んじる
供物(くもつ)やお供えは、飾り立てることよりも「心を込めて用意する」ことが何より大切です。
真宗大谷派では、供花や果物などを控えめに整え、清らかで落ち着いた雰囲気を重んじます。
|
種類 |
内容 |
備考 |
|
供花 |
白・黄・淡い色の花が中心 |
原色や派手な花は避ける |
|
供物 |
果物・お菓子など日常の食べ物 |
酒類・肉類は避ける |
|
お香 |
落ち着いた香りのもの |
匂いが強すぎないものが望ましい |
飾りよりも「心を映す場」であることを意識し、清潔で静かな空間を整えることが真宗大谷派の美しさです。
服装は「黒を基調に控えめに」|真宗大谷派の法要では派手な喪服を避ける
法要の服装は、「悲しみを飾らない」ことが基本です。
真宗大谷派では、黒を基調とした控えめな服装を推奨しています。
男性は黒いスーツ、女性は光沢のない黒のワンピースやスーツが一般的です。
アクセサリーはできるだけ控えめにし、靴やバッグも黒で統一します。
また、数珠は真宗大谷派門徒用(房が紐房で「蓮如結び」がされているタイプなど)を使うのが望ましいです。 装いは見せるためではなく、仏さまに心を向けるためのもの。
落ち着いた身だしなみが、法要の雰囲気を穏やかに保ちます。
お布施は「読経への感謝」|金額よりも感謝の気持ちを伝える姿勢が大切
お布施は「僧侶への謝礼」ではなく、仏さまへの感謝を形にしたものです。
そのため、金額に明確な決まりはありません。
地域や法要の規模にもよりますが、目安としては以下の通りです。
|
種別 |
一般的な金額の目安 |
|
法要(自宅・会館) |
30,000円〜50,000円前後 |
|
納骨法要 |
10,000円〜30,000円前後 |
|
報恩講など年中行事 |
志(気持ち)として包む |
封筒には「御布施」と表書きし、名前はフルネームで記入します。
僧侶に直接渡す際は、丁寧に合掌して「本日はお世話になります」と伝えるとよいでしょう。
真宗大谷派の法要と他宗派の違いは「祈りの対象」と「供養の目的」にある
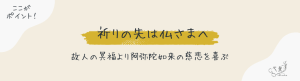
真宗大谷派では、祈る相手が仏さまであることが他宗派との大きな違いです。
多くの宗派が「故人の冥福を祈る」ことを目的とするのに対し、真宗大谷派では「仏さまの慈悲に感謝し、その教えに耳を傾ける」ことが中心です。
|
比較項目 |
真宗大谷派 |
他宗派(例:曹洞宗・浄土宗など) |
|
祈りの対象 |
阿弥陀如来 |
故人・先祖の冥福 |
|
法要の目的 |
仏の教えに感謝し、生を見つめる |
故人の救い・成仏を願う |
|
焼香回数 |
1回 |
2〜3回が一般的 |
|
お経 |
正信偈・念仏 |
各宗派独自の経典 |
この違いを理解すると、形式だけでなく「なぜそうするのか」という背景が見えてきます。
真宗大谷派の法要は、“祈り”ではなく“感謝と気づき”の場なのです。
まとめ|真宗大谷派の法要は“感謝と気づき”を深める時間
真宗大谷派の法要は、亡き人を偲ぶだけでなく、今を生きる私たちが感謝を新たにする時間です。
形式や正しさにとらわれすぎず、仏さまの教えに耳を傾けながら、静かに手を合わせることが何より大切です。
- 故人を通じて「いのちのつながり」に気づく
- 感謝の心で供養を行う
- 教えにふれることで、自分の生き方を見つめ直す
これらを意識すれば、どんな法要も自然と温かい時間になります。
阿弥陀如来の慈悲に包まれるように、感謝の心で穏やかに手を合わせる――
それが、真宗大谷派の法要が伝え続けてきた大切な姿です。