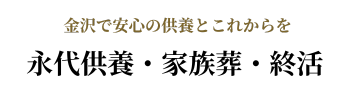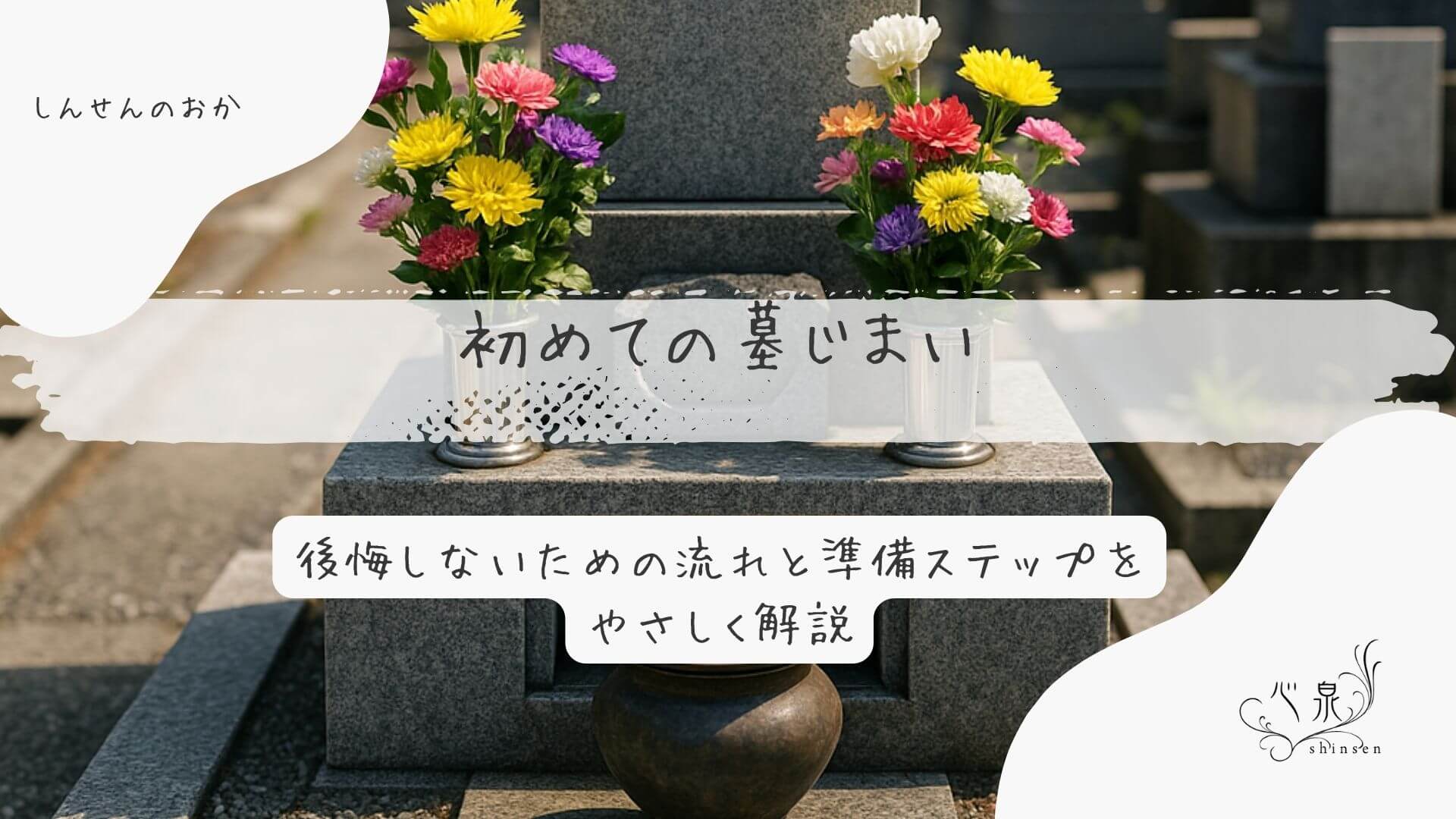「遠方の墓地を守るのが難しくなってきた」「子どもに負担をかけたくない」
そんな想いから、墓じまいを考え始める方が増えています。
しかし、いざ進めようとすると「何から始めたらいいのか」「寺院への相談はどうすれば良いのか」と戸惑う場面も多いものです。
墓じまいは、単なるお墓の撤去ではなく、“故人と家族の心を整理する大切な時間”でもあります。
心泉の丘では、これまで多くのご家族のご相談を受けてきましたが、丁寧に手順を踏めば、どなたでも安心して進めることができます。
この記事では、初めて墓じまいを考える方に向けて、流れ・費用・手続き・マナーまでをわかりやすく整理しました。
読んでいただくことで、必要な準備と心構えが自然と整い、迷うことなく次の一歩を踏み出せるはずです。
焦らず、一つひとつ進めていきましょう。
墓じまいは「お墓を撤去して遺骨を移す手続き」|まず全体の流れを理解しよう
墓じまいとは、お墓を閉じて、遺骨を別の場所へ移す「改葬(かいそう)」の手続きを行うことです。
古いお墓を撤去して更地に戻すだけでなく、新しい納骨先を決め、行政の許可を得て遺骨を移動させるまでが一連の流れです。
多くの方が不安を感じるのは、関係者の調整と行政の手続き。
けれど、全体像を把握しておけば決して難しいものではありません。
おおまかには、
「親族との相談 → 寺院・霊園との連絡 → 改葬先の決定 → 役所での申請 → 石材店による撤去 → 納骨」
という流れで進みます。
墓じまいは、物理的な作業だけでなく、故人への感謝を新しい形に変えていく過程でもあります。
慌てず、丁寧に段取りを整えることが、後悔のない選択につながります。
墓じまいの基本の流れは6ステップ|事前相談から改葬まで順を追って進める
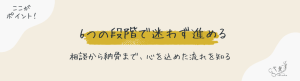
① 親族と相談して合意を得る|トラブル防止の第一歩
まず最初に、親族や関係者と意見を共有します。 「なぜ墓じまいを行うのか」「遺骨をどこに移すのか」を丁寧に説明し、全員の理解を得ることが大切です。
反対意見が出る場合もありますが、想いを共有することから始めましょう。 この段階での誠実な話し合いが、後のトラブル防止につながります。
② 寺院や霊園に連絡し、閉眼供養の日程を決める
墓じまいでは「閉眼供養(へいがんくよう)」を行います。
これは、これまでお墓に宿っていた“仏の魂”を抜き、新しい供養の形へ移るための大切な儀式です。 寺院に相談し、日程とお布施の目安を確認しましょう。
③ 改葬先(永代供養墓・納骨堂など)を選んで予約する
遺骨を納める場所を決めます。 永代供養墓、納骨堂、樹木葬など、選択肢はさまざまです。
「管理のしやすさ」「費用」「立地」などを比較して、自分たちの想いに合う供養先を選びます。
④ 改葬許可申請書を役所で取得・提出する
新しい納骨先が決まったら、現在の墓地のある市区町村役場で「改葬許可証」を申請します。 受入証明書(新しい納骨先から発行)と、埋蔵(収蔵)証明書(現在の墓地管理者から発行)を添えて提出します。
これが行政的に墓じまいを認めてもらう手続きです。
⑤ 石材店に依頼してお墓を撤去する
改葬許可証を受け取ったら、石材店に撤去を依頼します。 費用はお墓の大きさや立地で変わります。 現地見積もりをお願いし、追加費用が出ないように内容を確認しておくと安心です。
⑥ 遺骨を新しい納骨先へ移し、納骨式を行う
最後に、遺骨を新しい納骨先に安置します。 納骨の際には、簡単な読経やお参りを行う場合もあります。 これまでの感謝を込めて、静かに手を合わせましょう。
墓じまいに必要な費用は平均20万〜50万円|内訳と節約のポイントを押さえる
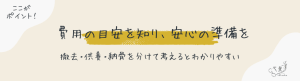
墓じまいの費用は、おおむね20万〜50万円ほどです。
金額に幅があるのは、墓地の規模や立地、石の種類、そして新しい納骨先の費用が大きく関係するためです。
|
項目 |
内容 |
費用の目安 |
|
墓石撤去・整地 |
解体・搬出・基礎撤去・残土処理など |
10万〜30万円 |
|
閉眼供養の御布施 |
僧侶への謝礼・読経料など |
3万〜10万円 |
|
改葬手続き費用 |
申請書・証明書の発行など |
数百〜数千円 |
|
新しい納骨先の費用 |
永代供養墓・納骨堂・樹木葬など |
3万〜50万円以上 |
費用を抑えるコツは、見積もりを複数取り、工程ごとに内訳を確認することです。
また、改葬先を先に決めてから撤去を依頼すると、手戻りが防げます。
「急がず比べる」ことが、結果的に安心にもつながります。
改葬許可申請は市区町村役場で行う|書類をそろえてスムーズに手続きを進めよう
改葬許可証がないと、遺骨を別の場所に移すことはできません。
申請時に必要な書類は次の3点です。
- 改葬許可申請書(役所で入手)
- 現在の墓地管理者が発行する「埋蔵(収蔵)証明書」
- 新しい納骨先が発行する「受入証明書」
提出先は、現在のお墓がある自治体の窓口です。
1〜2週間程度で許可証が交付されるため、その後に撤去と納骨の準備を進めましょう。
不安な場合は、寺院や専門業者に相談すると、書類のチェックや提出代行も依頼できます。
寺院へのお布施は感謝の気持ちを込めて|閉眼供養・永代供養の相場とマナー
お布施は「ありがとう」の気持ちを表すもの。
金額の相場は、閉眼供養で3万〜10万円程度が一般的です。永代供養料(新しい納骨先の費用)は、これとは別に必要となります。
表書きは「お布施」または「御供」とし、直接手渡しするのが丁寧です。
不安な場合は、寺院に包み方や金額の目安を相談して構いません。
何より大切なのは、長年お守りいただいた感謝を伝える気持ちです。
親族トラブルを防ぐには「共有」と「説明」が鍵|事前の話し合いで後悔を減らす
墓じまいは家族の想いが深く関わるため、意見が分かれることもあります。
「誰が決めたのか」「どんな意図で行うのか」が不明確なまま進めると、後に誤解が生まれやすくなります。
話し合いでは、理由・費用・日程・新しい納骨先・閉眼供養の日取りをまとめたメモを共有しましょう。
また、法要や供養の形を残すために、お墓の写真を撮ったり、墓誌の文字を記録しておくのもおすすめです。
“形を変えても、想いは受け継がれる”という意識を持てば、対話は穏やかにまとまっていきます。
墓じまい後は「新しい供養先」を選ぶ|永代供養・納骨堂・樹木葬の違いを知ろう
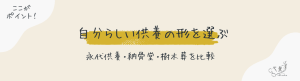
新しい納骨先を選ぶときは、「安心して供養を続けられるかどうか」が大切です。
それぞれの特徴を比較してみましょう。
|
供養形式 |
特徴 |
費用の目安 |
向いている方 |
|
永代供養墓 |
寺院や霊園が永続的に供養を行う |
3万〜30万円 |
継承者がいない方・費用を抑えたい方 |
|
納骨堂 |
屋内型で天候に左右されず参拝しやすい |
10万〜60万円 |
駅近やアクセス重視の方 |
|
樹木葬 |
自然に還ることを大切にする形式 |
10万〜50万円 |
自然志向・静かな環境を望む方 |
どの形にも「安心して託せる場所」を選ぶことが共通の目的です。
事前に現地を見学し、清潔感・アクセス・管理体制を確かめておくと安心です。
墓じまいをスムーズに進めるには専門業者のサポートが安心
墓じまいは、寺院や行政、石材店など複数の手続きが並行して進みます。
時間に余裕がない方や遠方の方は、専門業者にサポートを依頼するのも良い方法です。
業者選びのポイントは次の3つです。
- 見積もりの内訳が明確である
- 寺院との調整に慣れている
- 改葬許可や書類代行の経験がある
信頼できる業者と寺院が連携すれば、手続きは滞りなく進みます。
心泉の丘でも、必要に応じて石材店や永代供養先をご紹介しています。
不安なまま一人で抱えず、まずは相談から始めましょう。
まとめ|墓じまいは「心の整理」と「手続きの段取り」が成功の鍵
墓じまいは、「お墓をしまう」というよりも、「新しいかたちで想いをつなぐ」ための準備です。
家族や寺院と協力しながら、必要な手順を一つずつ進めることで、安心して次の供養へと移ることができます。
焦らず、まずは現状を整理し、改葬先を見学することから始めてみてください。
心泉の丘では、永代供養・室内納骨のご相談を随時承っています。
どんな小さなことでも、お気軽にお声かけください。
皆さまの想いが、静かに、やさしくつながっていくお手伝いができれば幸いです。