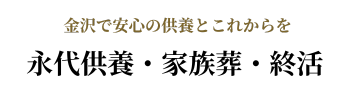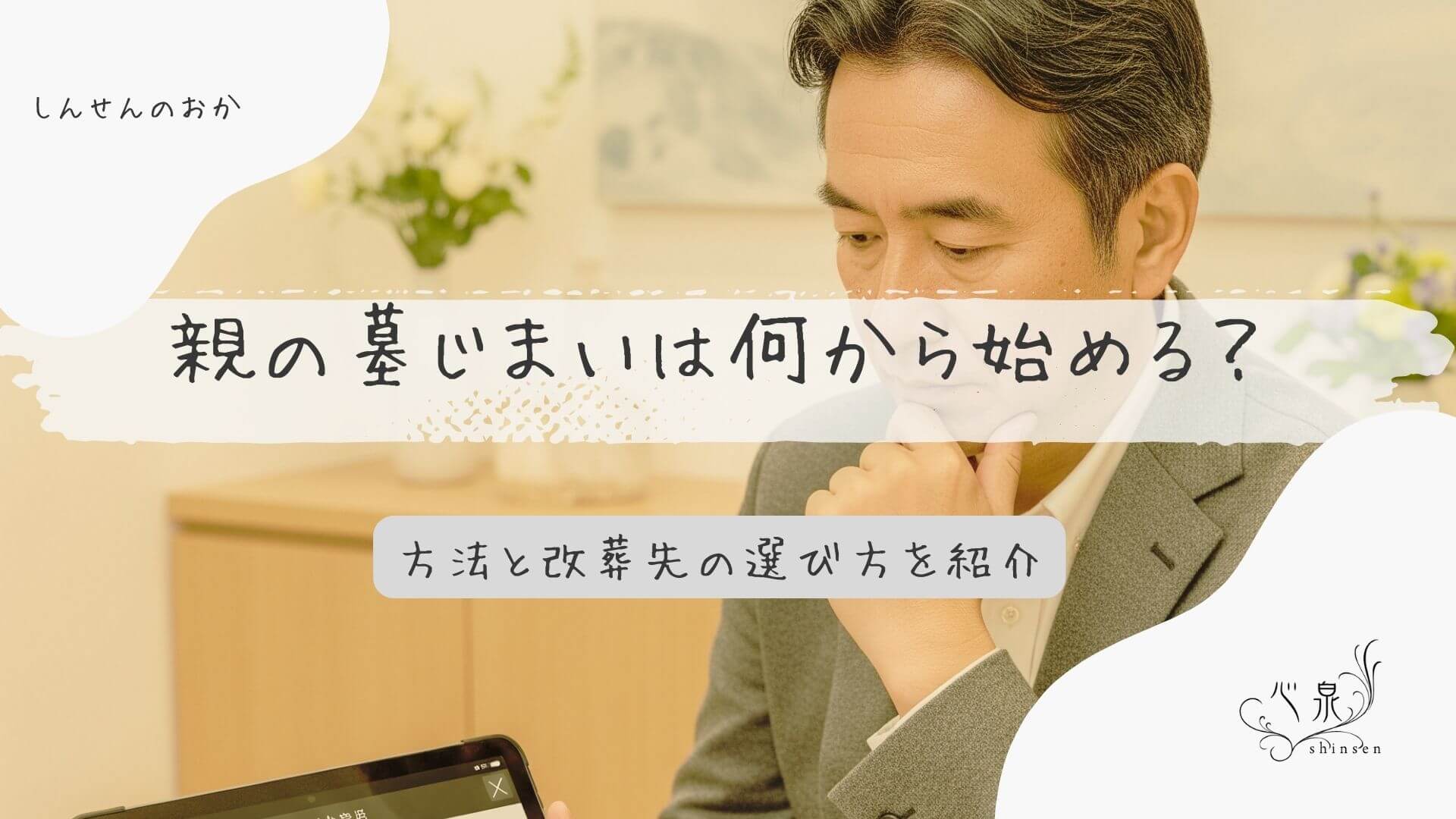- 親の墓じまいを考えているが、どこから始めればいいか分からない
- 寺院や親族への説明が難しそうで不安
- 費用や手続きの流れを知りたい
このような悩みを抱える人は年々増えています。少子高齢化や遠方への移住で従来のお墓を守るのが難しくなり、「墓じまい」を選択する家庭が増加しているのです。
ただし、親のお墓を整理するには親族間の同意や役所の手続き、寺院との調整などが必要で、流れを理解していないとトラブルに発展することもあります。
この記事では、親の墓じまいを検討している方に向けて、手順・必要書類・費用の目安・改葬先の種類をわかりやすく解説します。
読めば、何から始めれば良いかが明確になり、後悔のないスムーズな墓じまいを進められるようになります。
親の墓じまいは親族の同意を得ることから始める
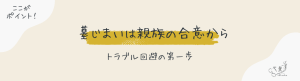
墓じまいの最初のステップは親族の同意を得ることです。
兄弟姉妹、親戚の中には「お墓を守りたい」と考える人もいるため、事前に話し合いを行い合意形成を図ることが欠かせません。
親族間で意見が割れると、寺院や霊園との交渉が進まず、最悪の場合は手続きが止まることもあります。早めに集まり、墓じまいの理由や今後の供養方針を説明するとスムーズです。
寺院や霊園への相談が墓じまいの第一歩になる
親族の同意を得たら、現在お墓がある寺院や霊園へ相談します。管理者に墓じまいの意思を伝えると、必要なお布施や手続き方法を案内してもらえます。
寺院によっては「離檀料」と呼ばれる費用を依頼される場合もあるため、トラブルを避けるため、事前に確認することをお勧めします。また、霊園の場合は管理事務所での解約手続きが必要です。
改葬には役所で改葬許可証を取得する必要がある
遺骨を別の場所へ移す場合、改葬許可証が必要です。これは役所で発行される書類で、旧墓地の管理者と新しい納骨先の証明が揃わないと取得できません。
改葬許可証の流れ
- 新しい納骨先を決定
- 受入証明書を取得
- 現墓地管理者から埋葬証明書を受領
- 役所で改葬許可証を発行
申請には数週間かかることもあるため、余裕を持って準備することが大切です。
閉眼供養と墓石撤去は専門業者に依頼するのが安心
墓じまいでは、遺骨を取り出す前に僧侶による**閉眼供養(魂抜きの儀式)**を行います。その後、石材店に依頼して墓石の撤去を進めます。
自分で解体することはできないため、必ず許可を持つ石材業者に依頼する必要があります。業者によって費用や作業内容が異なるため、複数社から見積もりを取り比較すると安心です。
墓じまい費用は30万〜150万円が目安となる
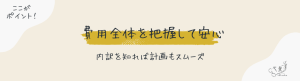
墓じまいの費用はケースによって異なりますが、墓石の撤去費用と改葬費用を合わせて30万〜150万円程度が目安です。
墓じまい費用の内訳目安
|
項目 |
費用相場 |
内容 |
|
石材店の撤去費用 |
20万〜50万円 |
墓石の大きさで変動 |
|
僧侶へのお布施 |
3万〜10万円 |
閉眼供養や法要 |
|
離檀料/ 離檀時に渡すお布施 |
5万〜20万円 |
寺院によって異なる |
|
改葬先費用 |
10万〜30万円 |
永代供養墓など |
事前に見積もりを複数取り、総額を把握してから進めると安心です。
改葬先は永代供養墓・納骨堂・樹木葬から選ぶのが一般的
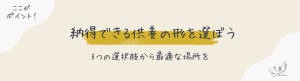
墓じまい後の遺骨は改葬先に納めます。一般的な選択肢は以下の3つです。
- 永代供養墓:寺院や霊園が永代にわたり供養。費用は10万〜50万円程度。
- 納骨堂:屋内施設に安置。費用は20万〜100万円程度。
- 樹木葬:自然葬の一種で、30万〜80万円が目安。
改葬先比較表
|
種類 |
費用相場 |
特徴 |
|
永代供養墓 |
10万〜50万円 |
跡継ぎ不要で安心 |
|
納骨堂 |
20万〜60万円 |
屋内型で参拝しやすい |
|
樹木葬 |
30万〜50万円 |
自然の中で眠れる |
どの方法が良いかは家族の希望やライフスタイルによって異なります。
親の墓じまいは費用と手順を理解すればスムーズに進められる
親の墓じまいは複雑に見えますが、流れを整理すれば安心して進められます。
- 親族の同意を得る
- 寺院や霊園に相談する
- 改葬許可証を取得する
- 閉眼供養と墓石撤去を行う
- 新しい納骨先に改葬する
これらを順序立てて進めれば、トラブルなく完了できます。
まとめ
親の墓じまいは、親族の同意・寺院への相談・改葬許可証取得・閉眼供養・墓石撤去・改葬先の決定という流れで進めます。
費用は30万〜100万円が目安で、改葬先は永代供養墓・納骨堂・樹木葬から選ぶのが一般的です。
👉 結論:親の墓じまいは正しい方法を理解すればスムーズに進められる。
これから墓じまいを検討する方は、まず親族間で合意形成を行い、複数の業者や納骨先を比較して検討を進めてください。